社交ダンスの種類がたくさんあるのは歴史が深いから!社交ダンスのことをもっと知ろう
社交ダンスと聞くとどんなイメージをするでしょうか?
燕尾服のシュッとした男性と煌びやかなドレスの女性が優雅に踊っているイメージ、
それとも、おじさんおばさんの習い事のイメージでしょうか?
社交ダンスのイメージはなんとなく
「敷居が高い」「難しい」「お金がかかる」「若者向けじゃない」
という風に思われがちですが、意外とそんなことはないのです。

ただ歴史が深く、ダンスの種類も豊富でいまいち全体像がつかみきれないので、
とっつきづらかったり敷居が高いように感じるのかもしれません。
まずは社交ダンスがどうやって始まったかの歴史と、
長い年月をかけて様々なジャンルに細分化した種類を知ってみましょう。
思っていたのと違う部分が見つかって、もっと興味を持つかもしれません。
社交ダンスを踊るのに歴史や背景などが分かるとより楽しく踊れそうですね。
ダンスの種類
それではまず社交ダンスの種類をざっと紹介します。
現在10種ダンスと言われる競技ダンスにもなっている社交ダンスと
基本形であるダンスとパーティーダンス4種が社交ダンスとして良く知られています。
競技ダンス:スタンダード5種
- クイックステップ
- スロー・フォックストロット
- タンゴ
- ワルツ
- ヴェニーズワルツ
競技ダンス:ラテンアメリカ5種
- サンバ
- ジャイブ
- チャチャチャ
- パソドプレ
- ルンバ
踊りを楽しむパーティーダンス4種
- ジルバ
- スクエアルンバ
- ブルース
- マンボ
聞いた名前のものも多いですね。
このダンス達がどのようにして誕生したかの歴史を紹介します。
主にヨーロッパとラテンアメリカが発祥の地の中心となっています。
社交ダンスの歴史

ます、なんで社交ダンスというか知っていますか?
「社交場」で男性と女性がペアになって踊るダンスのこと、
が名前の由来と思っている人が多いと思います。
海外からダンスの文化が入ってきたのは明治10年くらいと言われています。
西洋の文化が盛んに取り入れられ鹿鳴館でも
煌びやかな舞踏会が開かれるようにもなっていました。
その時に、このダンスのことを「Sociality Dancing」と
説明を受けたときに「Social Dance」と聞き違え、
直訳して社交ダンスとなった。という説が有力とされています。
余談ですが、2024年(令和6年)に新紙幣が発行されることになりますが、
その一万円札の肖像画として内定している「渋沢栄一」さんはパリ万博の幕府使節で舞踏会に出席し、
西洋のダンスに好印象を持った記録が残されていました。
英語圏では社交ダンスのことを「Ballroom dance(ボールルームダンス)」と呼びます。
日本語で直訳すると「舞踏室の踊り」となります。
最近では日本でも社交ダンスの練習場のことをボールルームと呼ぶところが
増えてきていますのでボールルームダンスという呼称が定着しつつあります。
ちなみにボールの語源はラテン語のbalare(踊る)からきています。
さて、日本に入ってくる前の社交ダンスはいつ始まったのでしょうか?
原型は12世紀ごろのヨーロッパで芸術や哲学が様々な変化を遂げた
ルネッサンス時代に始まったとされています。
広間で輪になりみんなで同じ動きをして踊るラウンドダンスが
社交ダンス文化の始まりと言われていました。

この時は、男女でペアになった踊るような形ではなく、
日本で言うなら盆踊りみたいな感じでした。
その後14世紀頃になると、ラ・ボルタと言う男女がペアになり
体を密着させながら踊るダンスがヨーロッパ中で流行りました。
貴族の間でも人気になり、社交界でのたしなみとして地位を確立し始めます。
18世紀になると現在の形に近くなり男女が向かい合い踊る形式になって、
貴族の部同会では若者に人気を博しました。
このころ踊られていたのがワルツです。
ワルツは諸説ありますが
- フランスプロヴァンス地方で踊られていた民族舞踏のヴォルト
- 南ドイツからオーストリアにかけて農民の間で踊られていた3/4拍子の民族舞踏のレントラー
- フランス人がアルマンドと名付けたドイツの民衆が踊っていたもの
がのいずれかがルーツになっていると言われています。
18世紀には上流階級に普及していた宮廷舞踏とともに典礼儀式などに
社交ダンスが取り入れられるようになり、上品なダンスとして認知はありましたが、
宗教の力が強かったことから男女が接触しながら踊る事はあまり印象はよくありませんでした。
特にイギリスでは男女が密着することへ嫌悪感や偏見がなくなることはありませんでした。
しかしその後、1837年イギリスの王妃・ヴィクトリア女王の戴冠の際に
社交ダンスが認められる大きな出来事が起きました。
オーストリアのウィーンを中心に活躍する作曲家ヨハン・シュトラウス1世が
『ヴィクトリア女王讃歌』というウィンナ・ワルツを捧げました。

作曲家ヨハン・シュトラウス1世の像
ヴィクトリア女王は楽しげに踊ったことが広く知られることになり、
他のヨーロッパの国々に遅れること20年、
ようやくイギリス社交界でもワルツが受容されました。
また同じ頃、民衆の間ではブルースやタンゴ(アルゼンチンタンゴ)までもが
広く普及していきました。
20世紀にはいると、イギリスでも社交ダンスが盛んにおこなわれるようになり、
ある夫婦がより優雅に踊るために「つま先で動いて踊る」従来のスタイルから、
「かかとから歩いて踊る」スタイルへ変化させたものを考案したことで、
競技ダンスとしても確立もされました。
さらに世界中でダンスの文化が浸透し多様化が進み様々なダンスがでてきました。
アメリカではジャズやブルースなどのブラックミュージックが登場したことにより
音楽も多様化しラテンアメリカのアップテンポなルンバやマンボ、
チャチャチャなどが普及していきました。
従来のダンスはワンステップ(one step)と言われる
一定の拍でステップを踏むスタイルでしたが、
ジャズなど拍が不規則でスイングするため対応できなくなったため
考案されたのが(Slow slow, Quick quick.) と早い拍と遅い拍の組み合わせを持った
フォックストロットが考案され、
アメリカで流行しスローフォックストロットと言うジャンルが確立しました。
これと併せてチャールストンと言うダンスと組み合わさったものが
ヨーロッパでも流行りました。

ルンバに関しては、発生当時スクエアルンバとキューバンルンバがありました。
ルンバは滑らかでゆっくりなテンポのダンスで、
拍子は4拍で2拍目と4拍目にアクセントがきて踊りやすいので
初心者にのおすすめのダンスとなっています。
スクエアルンバが1拍目から踊りだすのに対し、キューバンルンバは2拍目から踊り出します。
1962年に英国教師協会がルンバは2拍目から踊り出すものとして
ステップを規定したことから競技ダンスで踊られるルンバはキューバンルンバが採用されました。
同じ時期のハーレムで競技ダンスの種目にもなっているジャイブの原型も発生しました。
ジャズに合わせてフォックストロットが踊られるようになり、
1930年ごろにはテンポの速いスイングジャスに合わせてダンスを楽しむようになりました。
フォックストロットではスイングジャズの速いテンポには追い付かないため、
テンポに合わせた新しいダンスが出現し、それがジャイブの原型となったジッタバーグです。
これが1940年頃にヨーロッパに伝えられてジャイブとなり、
60年代にステップなどを細かく規定しジャイブが競技種目として定められました。
1920年代は世界中でダンスの多様化が進み、
スペインでも競技ダンスになっているパソドプレが誕生しました。
闘牛で闘牛士が入場するときの曲の総称として定義されていました。
このころのこのダンスの名前は「スパニッシュ・ワンステップ」という名で広がり、
ダンスの中心であったパリでも流行しました。
パソドプレはパソとも呼ばれ、スペイン語で「ダブルステップ」を意味し、
マーチ(行進曲)の音楽に合わせて踊るダンスです。
このダンスは闘牛をイメージしており、男性がマタドール(闘牛士)役、
女性はケープや牛、フラメンコダンサーを演じるなど曲や構成によって役は変わります。
また、このダンスの特徴としては男性が主役として立ち回り、
力強いステップで優雅さではなく勇ましさにフォーカスを当てています。
このころ日本でも上流階級に社交ダンスは流行りましたが
第2次世界大戦の開始ともにダンスホールが閉鎖されそれとともに衰退していきました。
競技ダンスの原型が登場してからしばらく時を置き、戦後1960年頃、優雅なダンスを見て楽しむことから、
踊って楽しむダンスへと革命がおこりました。
マンボと言う組んで踊らないダンスが登場しました。
このことにより相手をリードすることなくステップのかけひきができれば、
誰でも気軽に踊れるということから大流行しました。
これ以降、組まずに踊れるツイストやゴーゴーなどが登場し、
アメリカではディスコブームになりました。
日本でも1970年代のディスコブームとなり、ダンスの住みわけが行われました。

形式にとらわれず好きなように踊るディスコスタイルが若者に好まれ、
社交ダンスは国際意識が強い中高年の男女に好まれるようになりました。
1996年「Shall we dance?」が大流行し、
中高年だけでなく若者の社交ダンス人口も激増しました。
これに合わせてサルサやアルゼンチンタンゴ、メレンゲ、
バチャータなど世界で流行っていた様々なダンスも日本で広まり
ダンスの認知が確立しました。
21世紀の現在では、さらに多様化が進みダンスの形も進歩していっています。
そして、インターネットの登場により多様化したダンスの情報を即座に共有できるため、
ダンスの技術も日進月歩で高まっています。
多様化に合わせて、社交ダンスの認知も広がり興味を持つ人が増えてきていますが、
やはり敷居の高いイメージが付きまとうので、やってみたいけどちょっと…と二の足を踏んでいる人も多いと思います。
そんな思いに応えて、初心者用の無料体験レッスンや
基礎を優しく説明したセミナーなども数多く開かれており、
参加しやすい環境も整ってきています。
競技ダンスのように細かくステップを規定するものもありますが、
ダンスは誰でも気軽に楽しんでほしいと思います。
初めての人にも優しいダンスに触れてみて、ちょっと体を動かしてみませんか?
高級な練習着など必要なく参加できるカジュアル社交ダンスをサニーダンススクールは提案しています。
あなたのファーストステップでダンスの楽しさを体験してみましょう。
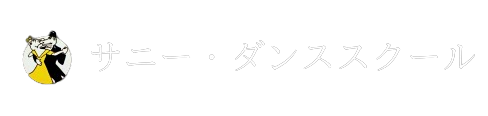




この記事へのコメントはありません。